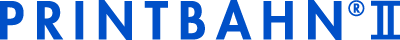名刺は、長年にわたりコミュニケーションツールのひとつとして活用されてきました。しかし、リモートワークが普及した現在、とくに紙の名刺の役割や必要性について見直す企業が増えています。デジタル名刺やSNSで代用できるという意見も出てきたからです。
それでもなお、一流企業や有名企業では、紙の名刺を利用し続けています。なぜ依然として名刺を活用しているのでしょうか。本記事では、紙の名刺が今も重要視される理由と、その効果的な活用方法について解説します。
紙の名刺の必要性は高い?低い?
デジタル化が進む現代において、紙の名刺は不要という意見が出てきました。リモートワークの広がりにより、対面での名刺交換の機会が減っている、またデジタル名刺やSNSでの情報交換が主流になりつつあるからです。
また、紙の名刺は管理に手間がかかる、コストがかかる、紛失のリスクなどの問題を抱えています。
しかし、SNSは利用していないひともいるのが懸念点です。SNSを通じた情報交換には限界があり、炎上リスクや企業・個人のなりすまし、セキュリティ上の問題も考慮しなければなりません。
また、デジタル名刺を導入する場合も、情報管理の手間やセキュリティのリスクはあります。データベースに侵入され不正利用される可能性や、誤ってデータが削除されるなどの危険があります。
デジタル名刺が広がりを見せつつはありますが、紙の名刺を所持していることは一人前のビジネスマンである証拠ととらえる方も多いのが現状です。名刺交換の際に、紙の名刺を所持していないと、相手からの印象を悪くしてしまう可能性があるのです。
そのため、近年ではデジタル名刺と紙の名刺を使い分ける方が増えています。オンライン商談や会議ではデジタル名刺を使い、対面では紙の名刺を使うなど、状況に応じてツールを使い分けています。
紙の名刺のメリット
デジタルツールが普及し、名刺のデジタル化が進むなかで、紙の名刺は時代遅れだと感じるかもしれません。しかし、紙の名刺には、デジタル名刺で得られないメリットが存在します。
安心感を与える
紙の名刺は「自分が本人である」という物理的な証明を行えるため、相手に安心感を与えられます。会社名、役職、連絡先といった情報が記載された名刺を直接手渡すことで、その人物が会社の正規の代表であることが一目瞭然だからです。
デジタル名刺も便利ではありますが、簡単に共有や変更が可能なため、信頼性に対しての不安感はどうしても残るでしょう。なりすましや詐欺のリスクもあります。
一方、紙の名刺はデジタルとは違い、コピーや改ざんが難しく、交換したという事実が確実に残るため、相手に対して信頼を築きやすくなります。信頼性が重視されるビジネスの現場では、デジタル名刺の普及が進んだとしても、視覚的かつ物理的に信頼を担保できる紙の名刺が重宝されるでしょう。
記憶に残りやすい
紙の名刺は自己紹介をそえて手渡しするため、相手の記憶に残りやすいという強みがあります。
一方、メールやテキストメッセージでは、文字情報のみが伝わるため、情報に溢れている世の中では記憶から風化してしまいます。紙の名刺を交換することで、相手の顔や表情、声のトーンといった非言語的な要素も伝わるため、より深く印象を刻めるのです。
人脈を広げるカギになる
紙の名刺は、ビジネスの現場で自然に会話を始めるきっかけになります。名刺を手渡すことで自己紹介がスムーズに行え、そこから自社や商材の説明へと話題を広げられるからです。
とくに大手企業の社長や役員クラスと交流する際は、紙の名刺が欠かせません。紙の名刺を所持していることが、ビジネスマンの基本と考えている方も多いからです。
名刺を受け取った相手がその時点では興味を示さなくても、後に必要になった際、に名刺を見返して連絡をもらえる可能性もあるでしょう。名刺には企業名や連絡先が記載されているため、後からでもスムーズに連絡が取れるからです。
紙の名刺のデメリット
紙の名刺は相手へ強く印象を残せる、安心感を与えられるなどのメリットがありますが、デメリットも存在しています。以下で詳しく解説します。
変更ごとに追加コストがかかる
紙の名刺のデメリットのひとつは、情報の変更ごとに追加コストがかかることです。職位や部署、連絡先などの情報に変更が生じた場合、そのたびに名刺の情報を更新して印刷する必要があります。このための印刷費用や手間が、企業にとって負担となるでしょう。
名刺を更新せずに使い続けると、受け取った相手に誤った情報を伝えるリスクがあり、信頼性を損ねる可能性があります。頻繁に情報が更新される企業では、コストの増加が課題です。
管理に手間がかかる
紙の名刺は管理に手間がかかります。名刺の在庫を常に確認し、なくなる前に新たに印刷を手配する必要があります。
もし名刺が足りないまま大切なビジネスの場に臨んでしまうと、取引先や新しいパートナーからの信頼に悪影響を及ぼす可能性がありです。そのため、名刺の在庫を常に確認し、適切なタイミングでの補充が求められるでしょう。
また、紙の名刺は物理的なものなので、紛失や破損のリスクがあるのが懸念点です。雨や飲み物で濡れる、汚れやシワがつく、うっかり紛失するなどが起きると、再発行の手間とコストがかかってしまいます。
名刺の活用方法
会社の予算を使って作成した名刺を、交換するだけで終わらせるのは惜しいです。ここでは、名刺を最大限に活かすための具体的な活用方法を紹介します。
社内での人脈を形成する
名刺は社内での人脈を形成するのに役立ちます。従業員が個々に持っている名刺情報を社内で共有することで、誰がどの業界やクライアントに繋がっているのかを可視化できます。
プロジェクトを進める際に、社内で特定の顧客との繋がりを持っている従業員を簡単に特定でき、商談が進みやすくなるでしょう。ただし、個々の人脈を可視化するためには、情報の一元管理が必要となります。
イベント参加者のリスト作成とその後のフォローアップ
顧客から受け取った名刺は、イベント参加者のリスト作成や、その後のフォローアップに非常に有効です。名刺を整理し、正確なデータベースを作成することで、新商品発表会やセミナー、ビジネスマッチングイベントなど、各イベントに最適な顧客層を特定できます。
さらに、名刺の情報を活用すれば、役職やニーズ、所在地に応じたパーソナライズされた招待状が作成可能です。過去のやり取りをもとに特別な招待メールを送ることで、顧客の参加意欲を高められるでしょう。
イベント後には、フォローアップメールを送り、商談の機会を広げましょう。とくに、商材に興味を示した顧客には、次のアクションを促す対応が求められます。
一方、まだ商材を利用していない潜在顧客に対しては、信頼構築が鍵となります。まずは、名刺交換のお礼メールを送り、継続的なフォローアップを通じて、信頼関係を深めていくことが大切です。
顧客層の分析とターゲティングの実施
自社の商材を利用してくれる顧客を特定し、効果的なアプローチ方法を見つけるためにも、名刺は有効です。イベントや商談で受け取った名刺をもとに、業界や役職、年齢、性別、地域ごとに分類することで、とくに興味を惹けそうな顧客に絞ってアプローチできます。
名刺を交換する際には、ただ情報を集めるだけでなく、相手の関心やニーズを自然な会話の中で引き出し、それらをメモしておきましょう。相手が直面している課題、抱えている悩みを聞き出すことで、より詳しく顧客のプロフィールを作り上げられます。
こうして収集したデータを使えば、顧客のニーズに合った新製品の開発や、優良顧客を特定して、上位商品や特別なサービスを提案するための販売戦略を立てることが可能です。名刺の情報と、営業の経験をうまく組み合わせることで、効果的なビジネス戦略がはかれるでしょう。
こちらの記事では、名刺の適正価格について解説しています。相場の費用や格安で作るメリット・デメリットも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
デジタル化が進んでも、紙の名刺は依然として価値があります。紙の名刺は、ビジネスマンの基本ツールなので、商談のスタートラインに立つには欠かせないものです。
名刺を手渡すことで、相手に安心感や強い印象を与え、コミュニケーションをより円滑にしてくれます。また、名刺に記載された情報をデータ化すれば、商材に興味を持っている方に直接アプローチできるのも大きな利点です。
プリントバーンのWEB名刺発注システムなら、名刺の発注時にかかる手間やコストを抑えられます。Web上で最大100件まで一度にプレビューでき、簡単に閲覧や修正が可能です。
変更点もひと目で確認できるため、印刷ミスがなくなります。FAXやメールでの校正作業が必要ないため、名刺発注にかかるコストを抑えられています。
さらに、QRコードの記載や外字対応、データ一括登録など、さまざまなニーズに応えられる機能も豊富です。ぜひこの機会に、プリントバーンをご検討ください。