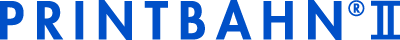新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークや在宅勤務をする機会は増えつつあります。場合によっては、オンラインで初対面の相手とコミュニケーションを取ることもあるのではないでしょうか。
その際、名刺が無くて不便に感じた経験のある人も少なくないでしょう。このような際に役立つのがWeb名刺です。
この記事では、Web名詞の概要のほか、使用するメリットやデメリットについて紹介します。名刺交換の方法や作成時のポイントも開設しますので、ぜひ参考にしてください。
Web名刺とは?
Web名刺とは、従来の紙ベースの名刺ではなくオンライン上で管理・共有できるデジタル形式の名刺です。オンライン名刺やデジタル名刺とも呼ばれ、近年注目されています。
Web名刺が普及した背景
デジタル名刺の利用が広がった要因として、ビジネスの国際化と感染症の流行による働き方の変化が挙げられます。もともと企業の海外展開が進むなかで、遠隔地との商談やリモートワークの必要性が高まっていたのが実情です。
ビデオ会議システムの発展により、離れた場所でもスムーズにやり取りできる環境が整っています。しかし、名刺交換に関しては、依然として対面でのやり取りが主流でした。
転機となったのは、新型コロナウイルスの影響によるオンラインビジネスの加速です。対面での打ち合わせが減少し、名刺を直接手渡す機会が激減した結果、相手の情報を手軽に管理できる手段として、Web名刺が急速に浸透しました。
紙の名刺との違い
デジタル名刺と紙の名刺の違いは、掲載できる情報量の差です。紙の名刺は限られたスペース内に必要な情報を記載するため、社名や氏名、役職などの内容に留まることが一般的です。
一方で、Web名刺はデジタルデータであるため、文字数やレイアウトの制約が少なく、企業の詳細やプロフィール、SNSのリンクなど多様な情報を掲載できます。また、データとして管理できるため、検索機能を活用して必要な名刺を素早く見つけられる点も強みです。
Web名刺のメリット
メリットは以下のとおりです。
- ●直接会わなくても交換できる
- ●内勤の社員とも簡単に名刺交換ができる
- ●ペーパーレス化を進められる
- ●Web名刺は作成・修正が簡単
- ●名刺を切らす心配がない
- ●自社サイトへ誘導しやすい
- ●情報管理がしやすい
それぞれのメリットについて解説します。
直接会わなくても交換できる
Web名刺はオンラインで簡単に共有できるため、対面せずに名刺交換が可能です。遠隔地にいる取引先やリモートワークを導入している企業間でも、スムーズに連絡先を伝えられます。
また、受け取った名刺をデジタルデータとして保存できるため、管理が容易で紛失の心配もありません。
内勤の社員とも簡単に名刺交換ができる
Web名刺は営業担当者だけでなく、オフィス内で業務に取り組む社員にとっても役立つツールです。従来の紙の名刺は対面での受け渡しが前提でしたが、デジタル名刺ならオンライン上で手軽に共有できます。
そのため、外出の機会が少ない社員でも、スムーズに人脈を広げることが可能です。とくに、社内外のコミュニケーションが重要となる職種では、デジタル名刺を活用することで、情報の交換が円滑になります。
さらに、リモートワークの普及に伴い、社内の異なる部署との連携もWeb名刺を通じて効率化できるため、組織全体の業務の流れがスムーズになるメリットもあります。
ペーパーレス化を進められる
Web名刺を活用すれば、紙資源の消費を抑えられるため、環境負荷の軽減につながります。紙の名刺は大量に印刷されることが一般的ですが、デジタル名刺なら印刷の必要がなくなり、ペーパーレスな業務環境を実現できます。
Web名刺は作成・修正が簡単
デジタル名刺は、情報の入力や更新が容易なメリットがあります。紙の名刺では記載内容に変更が生じた際、新たに印刷する必要がありましたが、Web名刺なら即座に修正できるため、コストや時間を削減できます。
また、作成手順もシンプルで、オンライン上で必要な情報を登録するだけで名刺が完成します。データとして保持されるため常に最新の状態を維持でき、誤った情報が伝わるリスクも軽減されます。
さらに、名刺を交換した後も相手に最新情報を提供し続けられるため、コミュニケーションがスムーズになります。情報の更新が容易な点は、Web名刺の大きな利点のひとつといえるでしょう。
名刺を切らす心配がない
Web名刺はデジタル形式のため、印刷した名刺を持ち歩く必要がありません。重要な商談や会議の際に名刺を忘れる心配がなく、常にスマートフォンやパソコンからいつでも見せられます。
また、紙の名刺と異なり、枚数を気にする必要がないため、急な名刺交換の場面でも対応可能です。オンラインで簡単に共有できるため、相手が遠方にいる場合でも、スムーズに連絡先を伝えられます。
自社サイトへ誘導しやすい
Web名刺にはURLを掲載できるため、受け取った相手がワンクリックで企業の公式サイトにアクセスできます。提供する商品やサービスの詳細をスムーズに伝えられ、興味を持った相手に対して効果的に情報を届けることが可能です。
また、名刺を受け取った側が改めて検索する手間が省けるため、見てもらえる可能性を高められるメリットもあります。オンライン上でのビジネスが加速するなかで、Web名刺を活用すれば、企業の存在感を高めることにもつながるでしょう。
さらに、プロフィールページやSNSアカウントへのリンクを掲載すれば、企業のブランディングを強化できる点も魅力です。情報発信のハードルが下がり、商談の機会を広げる効果が期待できます。
情報管理がしやすい
Web名刺はデータとして保存できるため、紙の名刺のように整理や分類に手間をかける必要がありません。検索機能を活用すれば、必要な名刺を瞬時に見つけられ、業務の効率化にもつながります。
また、企業全体で統一されたデジタル名刺システムを導入すれば、社員間での情報共有も容易になります。従来の名刺管理では個々の社員が独自に管理していたため、必要な情報が分散しやすい傾向にありましたが、Web名刺なら一元管理が可能です。
Web名刺のデメリット
さまざまなメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
- ●セキュリティ対策が必要
- ●企業単位での管理が難しい
- ●Web名刺を利用している人がまだ少ない
- ●インターネット接続が必要不可欠
- ●月額料金や初期費用が発生する
- ●デザインや個性のアピールが難しい
- ●社内ツールとの連携が難しい場合がある
それぞれのデメリットについて解説します。
セキュリティ対策が必要
Web名刺はクラウドやパソコン上に保存されるため、サイバー攻撃や不正アクセスのリスクを伴います。ハッキングによるデータの改ざんやウイルス感染による情報の破損が発生すると、企業の信頼にも影響を及ぼす可能性があります。
また、名刺情報の誤送信や外部への流出が起こると、個人情報が悪用される危険性もあるため、注意が必要です。取引先の連絡先や役職などのデータが第三者に渡ると、意図しない営業行為や詐欺被害につながることも考えられます。
こうした事態を避けるために、Web名刺を利用する際は以下のような対策を講じることが不可欠です。
- ●アクセス制限
- ●データの暗号化
- ●セキュリティソフトの導入
企業全体で情報管理のルールを統一し、安全な運用を心がけましょう。
企業単位での管理が難しい
多くのデジタル名刺アプリは個人向けに設計されているため、企業全体での一元管理が難しい課題があります。紙の名刺であれば、社内のルールにもとづいて統一したデザインやフォーマットで作成できます。
しかし、Web名刺は使用するツールやプラットフォームによって形式が異なり、管理が煩雑になりやすいです。また、どの社員が誰と名刺交換を行ったのかを正確に把握するのが困難な点も課題として挙げられます。
さらに、紙の名刺とデジタル名刺を併用する場合、それぞれの管理が別々に行われます。その結果、発注や更新作業にかかる手間が増え、担当者の負担が大きくなる可能性も考えられます。
Web名刺を利用している人がまだ少ない
デジタル名刺の利便性が注目される一方で、利用者の数は依然として多くはありません。とくに、ビジネスシーンでは従来の紙の名刺交換が根付いており、多くの企業や個人が従来の方法を継続しているのが現状です。
また、オンライン名刺を活用するには、相手側にも同様のシステムが導入されていることが前提となります。しかし、デジタルツールの導入に慎重な企業も多く、Web名刺のスムーズな交換が困難なケースもあるでしょう。
インターネット接続が必要不可欠
Web名刺を活用するには、パソコンやスマートフォンなどのデバイスと安定したインターネット環境が欠かせません。ネットワークが利用できない状況では、名刺の閲覧や共有ができず、ビジネスシーンでの柔軟な対応が難しくなります。
さらに、デバイスのバッテリー切れや通信障害が発生した場合、名刺交換がスムーズに行えなくなる可能性もあります。商談やイベントなど、リアルタイムでの情報共有が求められる場面では、充電環境の確保や予備の通信手段を準備しておくことが重要です。
月額料金や初期費用が発生する
Web名刺の導入には、プラットフォームやアプリの利用料金が発生する場合があります。無料で利用できるサービスもありますが、企業向けの高度な機能を備えたシステムでは、初期設定費用や月額料金がかかるケースが一般的です。
また、導入後の維持費用も考慮する必要があります。たとえば、社内で一元管理する場合や名刺管理システムと連携させる場合は、追加のカスタマイズ費用が発生する可能性があります。
デザインや個性のアピールが難しい
Web名刺はテンプレートをもとに作成されることが多く、デザインの自由度が制限されるケースがあります。背景デザインやロゴの配置、画像の挿入に制約がある場合も多く、印象を強める工夫がしづらい点もデメリットとして挙げられます。
したがって、デザイン性を重視する業界では、画一的なフォーマットではブランドの魅力を十分に伝えられない可能性があります。
社内ツールとの連携が難しい場合がある
Web名刺の導入にあたっては、既存の社内システムとの互換性を考慮する必要があります。多くの企業では、顧客管理システム(CRM)や社内データベースを活用しています。こうしたシステムとスムーズに連携できなければ、データの一元管理が難しくなるでしょう。
また、専用のオンライン名刺サービスを導入する場合、従業員への利用方法の周知や運用ルールの整備が必要です。システムのカスタマイズやセキュリティ対策には専門的な知識が求められるため、IT部門の負担が増加することも考えられます。
PRINTBAHNⅡでは、Web上で完結する名刺発注システムを提供しています。専用ソフトが不要で、専門知識がなくても3分で簡単に発注できます。導入実績7,000社以上のPRINTBAHNⅡで、名刺の発注業務を効率化しましょう。
Web名刺の交換方法
Web名刺の交換は、従来の名刺交換とは大きく異なります。事前に手順を把握することで、よりスムーズな名刺交換が可能となります。主な交換方法は、以下のとおりです。
- ●名刺情報をPDFにして相手にメールで送信する
- ●Web会議の背景に名刺情報を表示する
- ●名刺情報をQRコードに変換して共有する
- ●刺交換機能を備えた名刺管理システムやアプリを利用する
それぞれの方法について解説します。
名刺情報をPDFにして相手にメールで送信する
デジタル名刺を手軽に共有する方法として、名刺情報をPDF形式に変換し、メールで送付する方法があります。メールであれば、紙の名刺を直接渡せない状況でも簡単に情報を伝えられます。
具体的な手順としては、まず紙の名刺をスキャンし、データをPDFまたは画像ファイルに変換します。その後、メールの添付ファイルとして送信するか、Web会議ツールのチャット機能を利用して相手に共有すれば名刺が届きます。
Web会議の背景に名刺情報を表示する
オンライン会議では、バーチャル背景を活用して名刺の情報を伝えるのもひとつの手です。氏名や役職、会社名だけでなく、メールアドレスやウェブサイトのURLなども記載できるため、相手に効果的な情報提供ができます。
対面での名刺交換が難しい状況でも、相手に自分の連絡先を認識してもらえるのが利点です。とくに、複数人が参加するオンライン商談やセミナーでは、発言の機会が少なくても自身の情報をアピールできます。
名刺情報をQRコードに変換して共有する
デジタル名刺の情報をQRコードに変換すると、簡単に名刺交換ができます。オンライン名刺のURLをQRコード化し、相手にスキャンしてもらうことで、手軽に情報を共有できるのがメリットです。
スマートフォンでの読み取りが可能であれば、Web会議での画面共有機能の利用やバーチャル背景にそのままQRコードを組み込むなど、シチュエーションにあわせた異なる方法で共有できます。
紙の名刺を使わずにスムーズな情報伝達を実現できますが、相手がQRコードを読み取る環境にない場合は活用が難しくなる点には留意しましょう。
※『QRコード』は(株)デンソーウェーブの登録商標です。
刺交換機能を備えた名刺管理システムやアプリを利用する
名刺交換の手間を省き、効率的に情報を管理する方法として名刺管理システムやアプリの活用が挙げられます。こうしたツールは名刺を撮影してデータ化し、電子的に保存・管理できるのが特長です。
一部の名刺管理サービスでは、オンライン名刺交換機能を備えており、Web会議中でもスムーズに相手の情報を取得できます。紙の名刺を手渡す必要がなく、データをそのまま社内の共有システムに登録できるため、情報管理の負担を減らせるでしょう。
Web名刺を作成する際のポイント
効果的なWeb名刺を作成するには、いくつかのポイントをおさえる必要があります。作成する際のポイントは、以下の4つです。
- ●含めるべき情報の優先順位を決める
- ●フォントやレイアウトを統一する
- ●情報を詰め込みすぎず文字の間隔や行間を意識する
- ●外注する際は利用目的や要望を明確に伝える
それぞれのポイントについて解説します。
含めるべき情報の優先順位を決める
Web名刺を作成する際は、記載する情報の優先順位を明確にしましょう。基本的な要素として挙げられるのは、以下のとおりです。
- ●企業名
- ●役職
- ●氏名
- ●連絡先
- ●WebサイトのURL
- ●SNSのアカウント
企業名を目立つようにして役職と氏名を配置すると、相手が一目で重要な情報を把握できるようになります。連絡先やURLは視認性を考慮し、フォントサイズを調整すると効果的です。
フォントやレイアウトを統一する
Web名刺を見やすくするためには、レイアウトとフォントの統一が欠かせません。複数のフォントを使用すると統一感が損なわれるため、注意が必要です。ゴシック体や明朝体など、視認性の高いフォントを統一して使用すると読みやすくなるでしょう。
レイアウトの工夫もポイントのひとつです。一般的には、企業名や役職・氏名を上部に配置して連絡先を下部に記載すると、視線の流れに沿ったバランスのよいデザインになります。
情報を詰め込みすぎず文字の間隔や行間を意識する
Web名刺のデザインでは、必要な情報を整理し、適度な余白を確保するのも大切です。情報を詰め込みすぎると視認性が低下し、相手に伝わりづらくなります。
こうした事態を避けるためには、文字の間隔や行間を適切に設定するのが有効です。各要素が明確になるため、見やすくなるでしょう。とくに、社名や氏名などの重要な情報は周囲に余白を設けることで視線を引きつけやすくなります。
外注する際は利用目的や要望を明確に伝える
Web名刺を外部に発注する際は、使用目的や期待する役割を明確に伝えましょう。営業活動で即座に受注につなげるための名刺なのか、自己紹介を目的としたものなのかによって、掲載する情報やデザインの方向性が変わります。
また、Web名刺を利用するシーンによっても見せ方が変わります。オンラインミーティングなどの背景に組み込む、名刺管理システムなどで交換するといった具体的なシチュエーションを伝えることで効果的な名刺作成が可能となります。
まとめ
Web名刺は、現代に適した新しい名刺の形態として注目されています。紙の名刺とは異なり、オンライン上で管理・共有が可能なため、対面での交換が難しい場面でもスムーズに活用できるのが特長です。
一方で、セキュリティリスクや導入コスト、企業単位での管理の難しさといった課題も存在します。そのため、適切な管理体制や運用ルールを整えることが重要です。また、従来の紙ベースでの名刺交換と比較すると利用者が少ない傾向にあるため、どちらも対応できるようにすることが大切です。